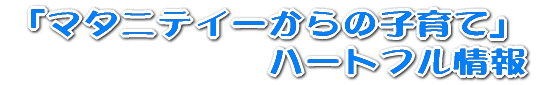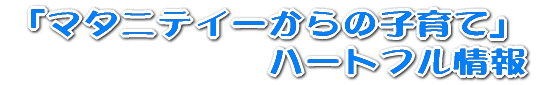| どうして最近のお母さんたちは母乳を飲ませなくなったのでしょうか? |
|
1 |
飲んだ量を知りたい〔昨日と比べどうか〕 |
| 2 |
他の子との体重比較(体重増加が成長の目安となる傾向がある) |
| 3 |
ミルクとの比較 |
| 4 |
哺乳瓶哺育は時・所を選ばなくて良い便利さが魅力 |
| 5 |
母乳の吸啜行為そのものが、その後の子供の成長発育要因としていかに大切な運動であるかを知らない |
| 6 |
母乳哺乳のトラブルに際、容易にあきらめて哺乳瓶哺育に切り替えてしまうケースが多い |
小児期からでも遅くはありません。
当医院では、『口唇閉鎖力測定器』(くちびるの閉じる力を測定できる機械)で検査をして、客観的なデータを用いて説明をしております。測定時の痛みは、くちびるを閉じるだけですので全くありません。
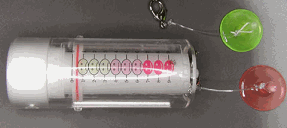 |